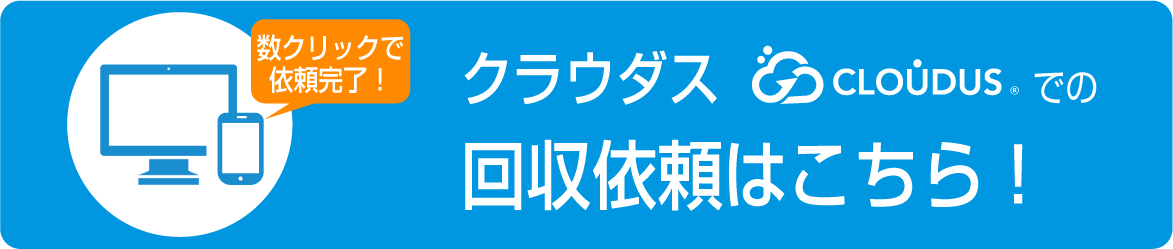そもそもBCPって?事業継続計画が抱える”形骸化”の壁
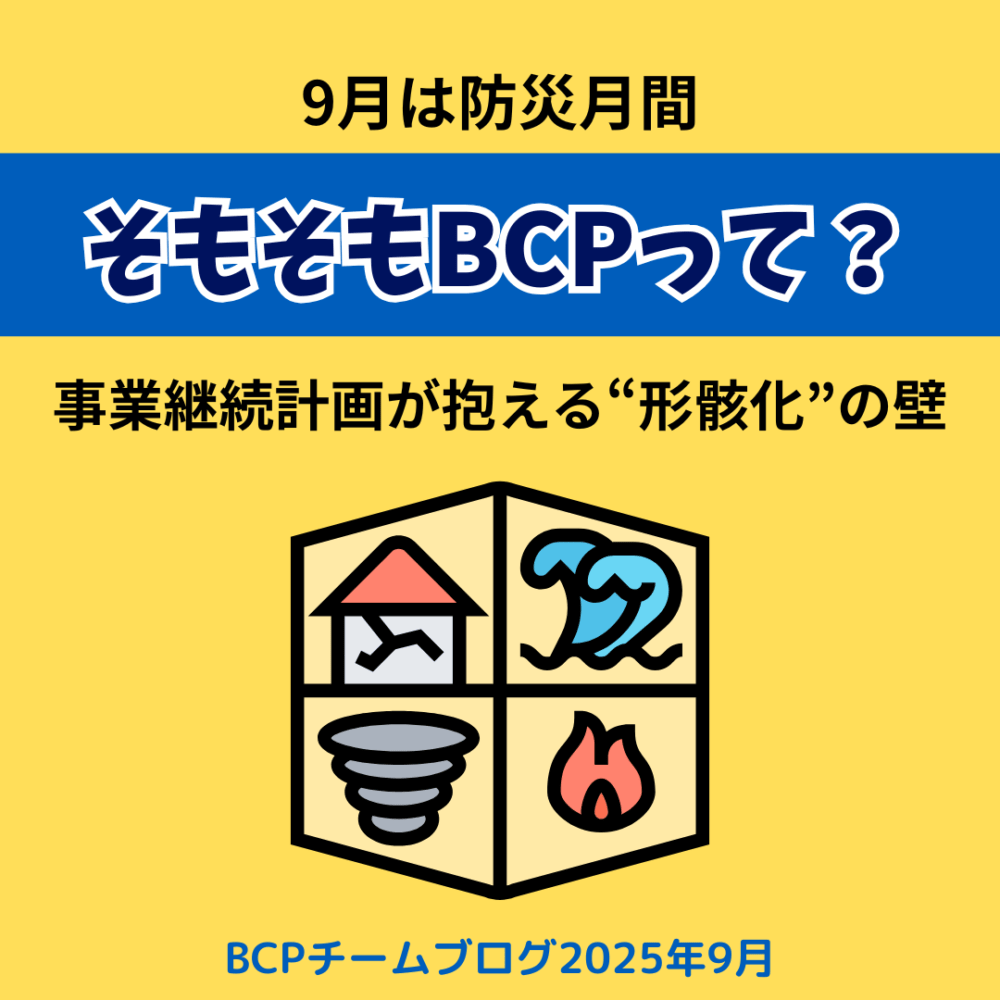
防災月間だった9月が終わり、10月1週目ですが、これは誰が何と言おうともBCPチーム9月のブログですw。今回もどうぞよろしくおねがいいたします。
秋の始まりと「防災月間」
残暑厳しいという言葉では物足りず、えげつない酷暑だった9月。最終週ですこし秋の気配を感じ、夏の残り香とともに台風や大雨に備える季節がやってきます。そんな9月は「防災月間」。その理由は、1923年に発生し未曾有の被害を出した関東大震災が9月1日に起きたこと、さらに台風の被害が頻発する月であることから、「災害に備えつつ知識を深める」ために制定されたのです。毎年9月は全国で防災訓練や啓発活動が活発に行われています。
BCP(事業継続計画)とは何か
BCP(事業継続計画)は、災害や予期せぬトラブルが発生した時、会社や組織がビジネスを途切れさせない・できるだけ早く復旧させるための「お守りみたいな作戦表」です。自然災害だけでなく、火災や感染症、サイバー攻撃など緊急時でも会社が重要な業務を継続できるようにするために不可欠なのが「BCP(Business Continuity Plan・事業継続計画)」。社員とその家族の安全を守るだけでなく、取引先や顧客との信頼関係を守るための盾でもあります。業務の優先順位や代替策、情報共有の仕組みなど具体行動を計画に盛り込むことで、緊急時にも落ち着いて動ける体制をつくるのが目的です。
なぜBCPが有効?
突然の地震や洪水、パンデミックやサイバー攻撃でも「これだけは守る!」という大切な業務をピックアップして、事前に優先事項・対策をきめておくと、実際に何か起きた時でも社員が慌てず落ち着いて動けます。BCPが機能すれば、
●早期復旧できるので会社の信頼が保てる
●お客様や取引先・地域へ責任ある対応ができる
●従業員を守りつつ、経営損失も最小で済む
災害時の対応力=「レジリエンス」の強い会社は、競争力や採用力でも優位です。
「作って終わり」にならないために
よくある失敗が「BCPは資料のまま眠りがち」問題。紙の計画書だけ準備して満足してしまい、実際は中身が古くて役立たない…責任者が辞めて誰もわからない…という例も多いです。記憶に頼らない・指示されなくても実行できる!を目指して 我々BCPチームでは
●定期的な訓練や見直し
●定型業務への組込み(例えば避難訓練や安否確認システムの導入)
●社内で「BCPの目的」を繰り返し共有
を続けています。大きな会社さんと違い 弊社ではBCP専任者ではなく、通常業務をしつつBCPチームタスクを担ってもらってます。だからこそ、一歩一歩のマイペースな歩みですが現場と計画の乖離・齟齬が生じにくいです。
そのために!レジリエンス認証が効く理由
「レジリエンス認証」は外部機関による“お墨付き”をもらうことで、BCPが「実際に機能してるか」客観的評価がつきます。第三者による定期審査があるので、形骸化防止・継続的な改善サイクルが強制されやすくなります。社員の危機意識も高まるし、対外的な信用もアップ。BCPを”続けてこそ意味あり”にする、かなり実用的な手段なんです。
さすが 防災月間らしい記事!というわけでなく、グループ2社目の寝屋川興業のレジリエンス認証登録更新審査が9月10月に控えているため今回のテーマに決めました。また10月に実施するBCP実動訓練にて計画の実効性を評価・見直しするために 現在BCPアップデート作業中です。もうあと数日やがな!ヤバイヤバイ
BCPは「作って終わり」じゃなくて「打ち出の小槌」です。レジリエンス認証は、それを現場でフル活用するための強力なブースター。しっかり言語化・手順化することで新人教育につなげることも有効だと感じています。
“もしも”をみんなで気軽に話し合うことがまず一歩
BCP(事業継続計画)も防災も、堅苦しく考えすぎず、“もしも”をみんなで気軽に話し合うことがまず一歩と考えます。秋の空のように、柔軟で変化に強い会社づくりを目指して、一緒に少しずつ備えを進めて、安心して働ける職場をみんなで作っていきたいですね!