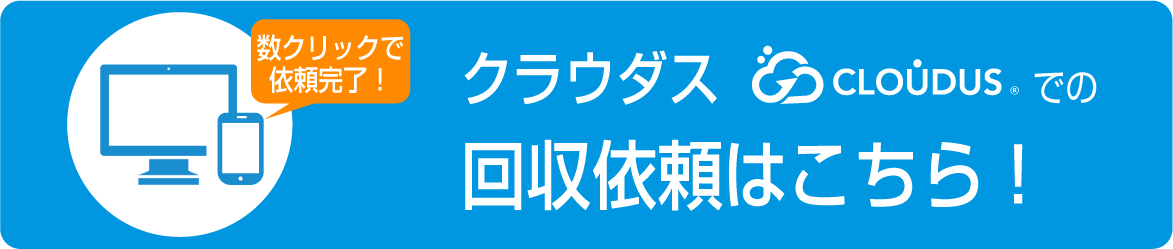ぼうさいこくたい2025 in新潟レポート&今できる支援情報

遅れ遅れで 8月のブログを9月にアップしています。そして記事は9/6,7と参加してきたぼうさいこくたい2025の話題。もう9月のブログでええんちゃうか?!と思いつつ、スタートします。どうぞよろしくおねがいいたします。
4度目のぼうさいこくたい
神戸、横浜、熊本に続き4回目の参加となったぼうさいこくたい2025。愛子さまがご参加されたことでニュースで見られた方も多かったのではないでしょうか。
さて会場は朱鷺メッセ。プログラムも会場も一切の下調べなく向かった新潟。空港でどういこうかと調べようにも この【朱鷺】が読めない。さぁさぁ困った。。。というところに 先の横浜ぼうさいこくたい、7月の万博セッションでご縁いただきました大阪男女いきいき財団の林さんと偶然同じ飛行機で!これ幸いとお声をかけさせていただき、会場まで連れてってもらいました。なんてラッキー!
さらに今回は、万博で防災トークセッションにともに登壇した2名の事業継続コンサルティングの専門家のお姉さまと一緒に参加し姦しく楽しい時間を過ごしました。完全ノープランだった私は姉様たちについて回ったおかげで BCAOや演習センターのセミナー、防災長準備室トークセッション、よんなな防災女子部のセミナーと、実践型・啓発型のセッションにも積極的に参加し、多様な防災リーダー・実務者と交流することができました!大阪男女いきいき財団の澤田理事長とも二日目お話でき 11月能登で合流することに♪いやぁ やっぱ動かなあきませんね。
急ぎ足でめぐった展示・ブース
今年の会場では、復興支援・共助・SDGs視点の防災備蓄、障がい者や外国人支援などマイノリティ配慮の展示が去年よりも目立っていたような個人感。私の中で具体的マクロな支援のフェーズになってきたからでしょうか。また、実務者企画委員会の「被災地支援コミュニケーション」やボランティア・学生連携プロジェクトなど、実践的な学びの場が広がり、個人の体験や意見が交差する空間となっていました。
2004年の中越地震や2024年の能登半島地震を経験した新潟での開催でしたので、その経験を「次世代へ伝える」事を主題とした展示やワークショップも多く、若い世代が「知識を広げ、行動でつなげる」姿勢を持って地域の災害対応力向上に貢献していることが強く伝わりました。被災地新潟ならではの現場感や記憶の継承が、団体・学生の双方から力強く発信されていて、来場者も改めて「自分ごと」として災害を考える機会になったと思います。災害経験を“教訓”で終わらせず、日常や未来へ活かそうとする北陸の実直さ、そして若者の主体的なまなざしに、純粋に感銘を受けました。











今我々にできる支援情報
今年のぼうさいこくたい2025では、写真洗浄の活動に取り組む「あらいぐま能登」さんのブースで、能登半島地震で被災した家族写真を実際に洗浄する体験をさせていただきました。地域の思い出を守る活動に触れることで、大阪で活動されている「あらいぐま大阪」さんでぜひお手伝いに参加したい、という思いを強くしました。

JQAN「支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク」のブースでは、支援現場での質や説明責任を高める取り組みについて直接お話を伺う機会を得ました。スフィアハンドブック=国際基準への理解や現場実践のための学びが、日本の防災コミュニティでも着実に広がっていることを感じました。残念ながら今年の研修に参加できなかったのですが、人々の権利を尊重できる避難所運営管理に欠かせないスフィア基準を学びたいと強く感じました。
熊本でのぼうさいこくたいですごく感銘を受けた 日本カーシェアリング協会さんのブース。今年も立ち寄らせていただきました。今現在 九州豪雨の被災地支援として、能登半島での支援活動を終わらせた車両の運搬ドライバーを募集されているようです。もちろん 車両も足りていないそうです。レンタカーを予約する。車を寄付するだけでなく、架け橋ドライバーという支援。さらに ふるさと納税でも支援できるそうですよ!あいはらさんちのレンコン おいしそう~
カーシェアリングについては 2024年10月のブログでも紹介していますので、良かったらご覧になってください~
今月もご笑覧いただきありがとうございました。次回のBCPチームブログをよろしくお願いします。たまシャチョーでした!